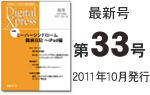赤めだか
2009年03月01日作成
立川 談春
著(扶桑社)
本書との出会い
落語ブームだそうだ。評者は、落語家立川談志の大ファンである(以下、立川流にならい談志師匠を家元と呼ぶ)。その弟子談春の随筆を書評の対象とすることになるのも何かの縁である。本書との出会いはまったくの偶然であった。仕事帰りにふらっと立ち寄った本屋で「講談社エッセイ賞受賞、マスコミ、各界で大絶賛の嵐」の帯が目にとまり手に取った。本書最後の「特別編その二 誰も知らない小さんと談志―小さん、米朝、ふたりの人間国宝」の部分を立ち読みした。
平成18年の独演会で米朝の作品「除夜の雪」を演ろうと決心し、直接米朝のお墨付きをもらうべく自宅を訪問し、稽古をつけてもらう話。同僚志らくに真打昇進で先を越され、さだまさしにグチったところ一喝され、改めて覚悟を決めたエピソード。自らの真打をかけた会に、家元の師匠であり絶縁状態にある柳家小さんに直接ゲスト出演を依頼した顛末。約40ページ、一気に読んだ。しびれた。感動で涙がにじんだ。巧みな文章。真情の吐露、笑いのセンス、そして底流に一貫して流れる落語への熱い想い。早速購入し、残りは自宅で丹念に読む。珠玉の名品に出会った喜びをかみしめながら。
立川談志との出会い
談春の親類もご近所も皆職人。中学生の頃は、腕一本で金が稼げる競艇選手になりたかったそうだ。しかし、身長が規定以上に伸びて終わり。漫才ブームのなか、図書館で落語全集にはまる。中学卒業間近、上野鈴本へ落語を聴きにいく企画があり、初めて家元の毒、才、存在感に触れる。そして運命の日。三宅坂の国立演芸場で行われた「立川談志芸能生活三十周年記念の会」で家元の古典落語、人情話の逸品「芝浜」を聴く。衝撃を受ける。そして弟子になることを決意する。ここからは行動の人、談春の面目躍如である。親からは勘当同然で高校を中退し、新聞配達での自活を条件に単独家元に弟子入りを懇請する。昭和59年3月、晴れて弟子入りが許され前座修行が始まる。17才の春。この段階でまだ名はない。1か月後、立川談春の名前をもらう。
前座修行
その昔、家元が自信を持って送り出した弟子が落語協会の真打昇進試験で落とされ、
家元激昂し、協会を脱会した事件があった。協会長は家元の師匠である柳家小さん。小さん師匠は家元を破門する。以来、立川流は、寄席という芸の発表の場と弟子の修行の場を失う。
立川流の二つ目(真打の手前)昇進基準は明確だ。古典落語の持ち根多50席、寄席で使う鳴り物を一通り打てること、歌舞音曲の理解、講談の修羅場を読むための基本技術の修得。判定者は家元。納得すれば合格。既に前座修行中の談々、関西、後から高田文夫の紹介で入門してきた良きライバル志らく。礼儀作法を身につけるための築地魚河岸修行(実際に働いたのは餃子屋さん)、家元からの初稽古、タクシーの中での稽古、辞めていく仲間、食い物の恨み、理不尽、ハワイ旅行。笑いと涙、前座修行時代が活写される。まさに談春の生き様事態が落語のよう。ちなみに、題名の「赤めだか」は、家元が庭の水がめに飼っている金魚のこと。いくらエサをやってもちっとも育たないので談春達は「あれは金魚じゃない、赤めだかだ」と言って馬鹿にする。前座時代を重ね合わせている。
時は流れ昭和63年3月4日、満席の有楽町マリオンで4人の二つ目昇進披露落語会が行われる。ゲストの口上の後、トリで上がった家元が選んだ根多は手慣れた十八番ではなく、初めての演目「包丁」。身をもって落語と向き合う姿勢を弟子達に見せる家元の凄味。後年、真打昇進をかけて家元の前で演る根多に談春も志らくも「包丁」を選ぶ。
評者不覚にも、まだ談春の落語を聞いたことがない。早速音源を手にいれよう。独演会にも行ってみよう。赤めだかが立派な金魚になった姿を確認するために。
(評者:Katsuyoshi.N)




 花や散るらん
花や散るらん